【】
②あの子らの碑
【更新日】2021年06月30日
| ② あの子らの碑 | |
|
|
|
 |
|
| 病床にあった永井隆博士の発案により,「原子雲の下に生きて」の本が出版され,その印税により造られ建立されました。 |
| 山里小学校の平和のシンボル「あの子らの碑」です。この「あの子らの碑」は、山里小学校の子どもたち、先生方、そして永井隆博士の思いがひとつになってできた碑です。 昭和20年8月9日、一発の原子爆弾によって長崎に住む多くの人々が犠牲になり、この山里小学校でも、1500人以上いた子どもたちのうち、1300人が亡くなりました。また、戦争に行かずに学校に残っていた先生方が32人いましたが、そのうちのほとんど、28人が亡くなりました。 十月になって授業が再開されましたが、そこに集まった子どもはわずか100人余りしかいなく、着ていた服は汚れてみすぼらしく、栄養失調で顔は青白く、はだしの者もいました。「教科書も鉛筆も帳面も、みんな焼けてしもうた」と泣きながら訴える子どもたちに、先生たちもただもらい泣きをするしかなかったそうです。 原子爆弾の投下から4年がたった昭和24年、生き残った子どもたち、先生方の原爆体験記が「原子雲の下に生きて」という本になりました。その本を発行してくださったのが永井隆博士です。 この「原子雲の下に生きて」は、親や兄弟を亡くした山里小学校の子どもたちの悲しみが切々と伝わってくる作文集でした。この本を購入した全国の多くの方々の涙を誘いました。 そして、この本が売れたお金が、子どもたちにも配られました。みんな日々の生活にも困る毎日でしたが、配られたお金の一部をこの「あの子らの碑」を建てる資金のため喜んで差し出したそうです。そうして集まった金額は当時のお金で4万円でした。 この碑を建てるために必要なお金は11万円だったそうですが、残りの7万円は永井博士が寄付してくださいました。 私たちが毎日普通に目にしているこの「あの子らの碑」ですが、山里小学校の子どもたち、先生方、そして永井博士の思いが形になって表れたものだったのです。だからこそ、私たちはこの碑、およびこの碑にこめられた思いを大切にしなければなりません。 新校舎の完成と共に今の場所に移された平和のシンボルは、こうした歴史を刻みながら、ずっと山里小学校の子どもたちを見守ってきました。きっと今の子どもたちが大人になり、その子どもが山里小学校に通うようになったとしても、この「あの子らの碑」はずっと子どもたちを見守ってくれることでしょう。なお、永井博士の言葉によれば、子どもたちがこの碑の上で遊んでもけがをしないように、低くずんぐりとした形にしたそうです。 |
|||
 |
 |
 |
 |
| 静かにたたずむ「あの子らの碑」。 | 8月9日には一輪の花を捧げます。 | これは11月の平和祈念式の日の朝。 | 登校した子どもたちが祈りを捧げます。 |
 |
 |
 |
 |
| 平和な毎日が続きますように。 | 花で埋め尽くされました。 | 毎日子どもたちを見守っています。 | 本校で行われるスポーツ大会などの折にも、この碑に祈りを捧げています。 |
| 昭和の頃、旧校舎の「あの子らの碑」 | |||
  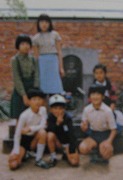 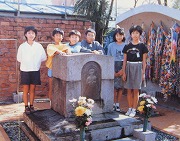  |
|||
| 今と違う場所にありましたが、昔からずっと「あの子らの碑」は、山里小学校の子どもたちを見守ってきました。 | |||
